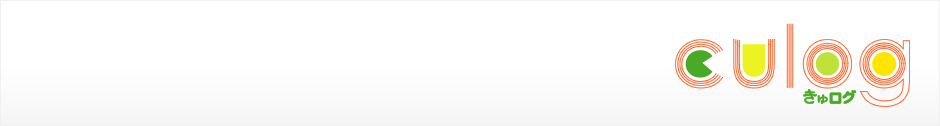先日、生け花のサークルのみなさんが、父の陶房へ陶芸体験教室にいらっしゃいました。

6月の作陶の様子。

素焼きを経て、2回目となる今回は、釉薬をかける作業。
まずは、やすりで作品の表面をなめらかにします。
炎天下、木陰を探しながらの作業でした。

そして、色見本を見ながら、好きな色を選びます。

出来上がりの見本色と、釉薬の色は同じでないので、不思議な気持ちになりながら
釉をかけていきます。
どんな出来上がりになるのか、本焼きの窯を開ける瞬間までわからないのが、陶芸の醍醐味。
みなさま、出来上がりをお楽しみに!
陶房の裏庭には、蓮の花が夏の空に向かって綺麗に咲いていました。

8月の茶室。

先生が水差しの「ふた」代わりに、蓮の葉を載せて、この時期にしか見ることのできない趣向を
見せて下さりました。
写真だとちょっと見にくいのですが、葉っぱの中心に水滴を置いて、涼を演出。

葉っぱの「ふた」を外したら、そのまま丸めてしまうので、お点前の最後には、
扇子を広げて置きます。

蓮は、水揚げが難しく、すぐにしおれてしまうので、数時間も持ちません。
10:00からのお稽古に合わせて、朝一番に切ったのですが、葉っぱの鮮度を保つことは、
難しかったです。
この日の掛け軸は、「一期一会」。
まさに、「今、この時、目の前の相手と心を尽くし合う」という精神的な贅沢を感じたひとときでした。
植物や花は、その存在そのものが、自然が作り出した美の一形態です。
さらに、いけばなでは、ひとの手を加えて、枝や葉や花の「形」、「色」、「空間」などを見極めて、余分と思われるものを省略しながら「自然の美とはちがう、ひとのおもいによる美」(※1)を作り出しています。
今回のいけばなの稽古での課題は、「単純化の極」。
テキスト(※2)では、以下のように述べられていました。
【単純化の極】
・・・それ以上省略すると、その植物素材ではなくなってしまう、いけばなではなくなってしまう、というぎりぎりまで作品のあり方を考えていくのです。ということは、極限まで単純化されたその作品は、逆にすべてを含んでいなければならないということ、つまり最少の要素で最大のものが表現されていなければなりません。・・・(※2:p76)

「どの枝を省略すればいいのか?」
枝と向き合いながら、吟味していると、いつのまにか、自分自身と向き合うことになります。
余分なものをそぎ落としていくと見えてくる本質。
「単純化」というのは、ただ簡単にすることではなく、強固な基礎があってこそ、表現できること。
これまで習ってきた基礎の重要性を痛切に感じました。

1本の枝と1輪の花をいけるのに、1時間以上かかってしまいましたが、
「基礎を積み重ね続けることの意義」を学んだ実りある稽古となりました。
・・・
【参考文献】
(※1)勅使河原 茜『草月のいけばな1[花型]』(2008,草月文化事業株式会社)
(※2)勅使河原 茜『草月のいけばな4[素材と空間]』(2008,草月文化事業株式会社)